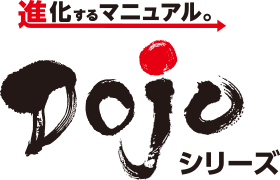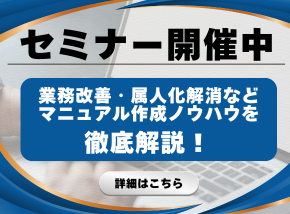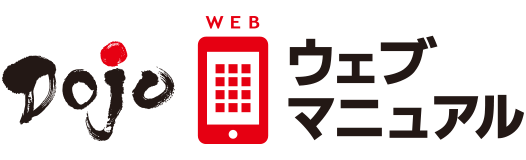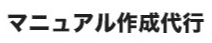業務マニュアルには、自社の業務フローの全体像や作業手順、注意点などの情報を効率的にスタッフへ伝える目的があります。マニュアルを運用することで、業務効率化や属人化解消などの効果が期待できます。これらを実現するためにも、手順書や操作マニュアルなどの資料は見やすく工夫して作成することが大切です。
見やすいマニュアルを作るには、一体どんなポイントを押さえれば良いのでしょうか。この記事では、見やすいマニュアルの作り方や、マニュアル制作時のレイアウトのコツ、避けるべき失敗例などのノウハウをご紹介します。マニュアル作成のご担当者様は、マニュアルを効果的に運用するために、ぜひ参考にしてみてください。
INDEX
1.見やすいマニュアルの特徴とは?
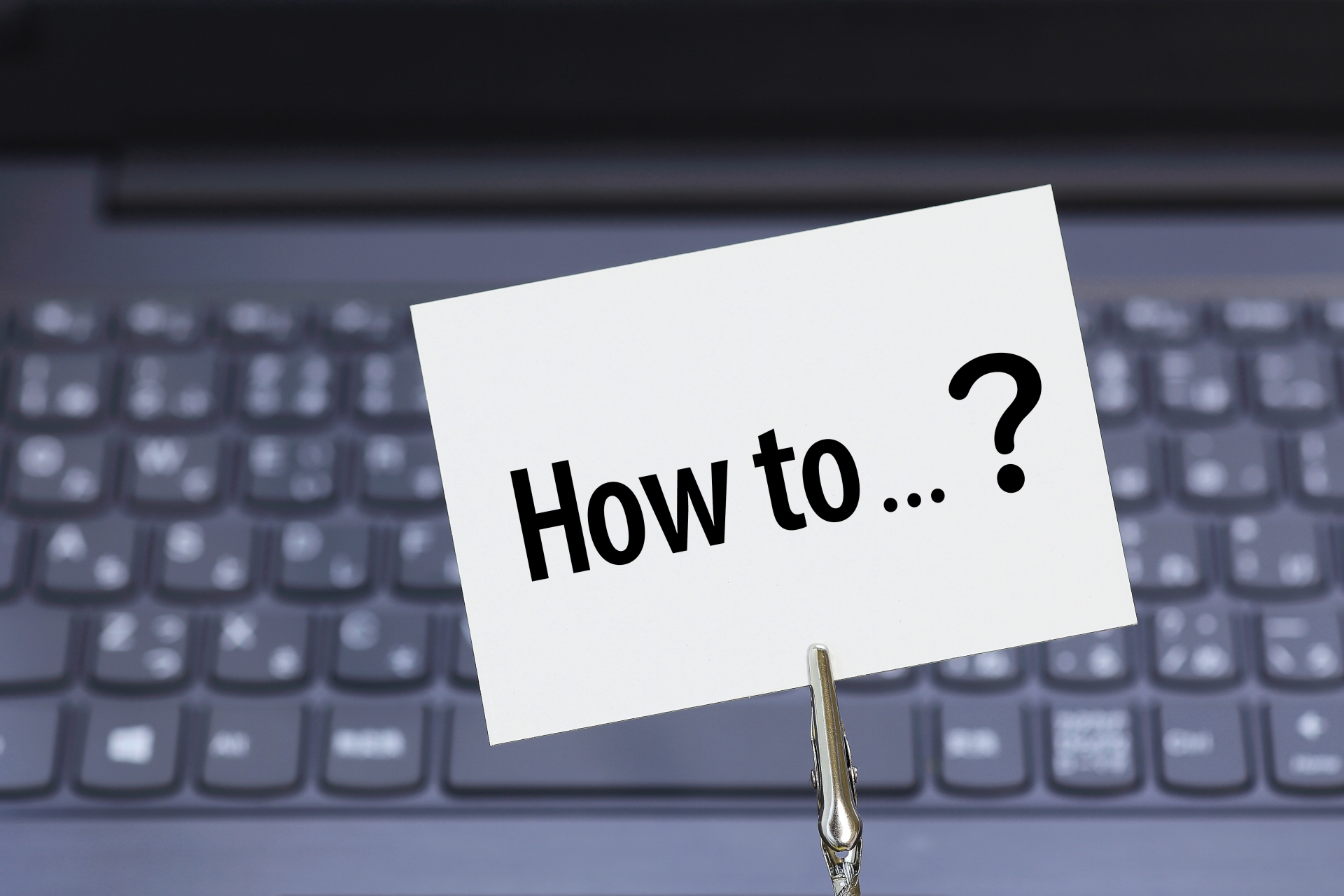
見やすいマニュアルと見づらいマニュアルには、一体どのような違いがあるのでしょうか。まずは、見やすいマニュアルの特徴を解説します。以下の特徴から、マニュアル作成で目指す完成形をイメージしてみましょう。
1-1.統一感のあるレイアウトにデザインされている
見やすいマニュアルは、レイアウトに統一感があります。マニュアル全体の情報が同様のルールに従って整理されているため、読者はどのページを読んでも必要な情報をすぐに見つけられます。その際、レイアウトは視認性が高く、ストレスなく読める状態が理想的です。
1-2.適度に図や画像が使用されている
見やすいマニュアルでは、文字のほかに図や画像などを活用して、補足説明が適宜行われています。例えば、業務の手順や操作方法などを説明するときは、文字だけでは直感的に理解しにくいことが少なくありません。図や画像による視覚的な効果によって、読者の理解を助けることが可能です。
1-3.階層的に説明が記載されている
見やすいマニュアルは、情報が階層的に説明されていて、読者が体系的に理解できる構成になっています。特に新人研修などで用いられるマニュアルは、膨大な情報を初心者の理解度に合わせて丁寧に説明することが重要です。情報が的確に整理されているマニュアルは、研修後の振り返りの場面でも役立ちます。
2.見づらいマニュアルの特徴
マニュアルを作成するとき、読者に漏れなく情報を伝えようとして、つい多くの内容を盛り込み過ぎてしまうことがないでしょうか。以下のようなマニュアルは、一般的に読者が見づらいと感じやすく、却って情報が伝わりにくくなってしまうため注意が必要です。
【見づらいマニュアルの特徴】
| ・1ページあたりの情報量が多すぎる ・使う色が多すぎる ・挿入している写真や図の画質が粗く見づらい ・まとまりのないレイアウトになっている |
1ページあたりの情報量が多すぎたり、使う色が多すぎたりすると、メリハリがなくなり重要な情報の見極めが難しくなります。また、せっかく読者の理解を助ける写真や図を活用しても、画質の問題で見づらくなっている場合は、視覚的な効果を十分に発揮できません。全体のレイアウトにまとまりがないと、ごちゃごちゃとした印象になり、読み手にストレスを与えてしまいます。
既存のマニュアルにこうした問題点がある場合は、以下でご紹介するポイントを参考にしながら、レイアウトの改善を行いましょう。
3.見やすいマニュアルの作り方の8つのポイント

ここでは、見やすいマニュアルの作成方法を8つのポイントに分けてご紹介します。誰が読んでも伝わるデザインにするために、以下のポイントを押さえておきましょう。
3-1.余白
文章や図表の間へ余白を効果的に使うことで、読者を特定の情報に注目させたり、情報の区切りを明確にしたりできます。このような視覚的な重要性を理解したうえで、適宜余白を取り入れると良いでしょう。その反対に、無駄な余白を作りすぎないよう注意が必要です。
| OK例 | 読者の視点を意識して余白を効果的に使っている |
|---|---|
| NG例 | 無駄な余白が多い |
3-2.フォント
文字のフォントは、基本的に1種類で統一したほうが読みやすくなります。視認性が高く、マニュアルの目的に適したスタイルのフォントを選びましょう。その反対に、複数のフォントを使うと読者に違和感を与え、読みづらくなるおそれがあります。また、閲覧環境に依存するフォントは避けるようにしましょう。
| OK例 | マニュアルの内容に適した1種類のフォントを使用している |
|---|---|
| NG例 | 複数のフォントが混在している、文字化けする可能性があるフォントを使用している |
3-3.文字の太さ・色
マニュアルの情報の中でも特に重要性が高い部分は、文字の太さや色を変えて強調すると良いでしょう。ただし、装飾が多すぎると重要な部分がどこかわかりづらくなるため注意が必要です。重要な部分のみに装飾を加えてメリハリをつけることで、より効果的にアピールできるようになります。
| OK例 | 重要な部分のみに装飾を加えている |
|---|---|
| NG例 | 装飾を多用している |
3-4.目次
マニュアルの冒頭に目次を作ると、読者が必要とする情報をスムーズに探しやすくなり検索性が高まります。目次を作成する際は、ひと目見ただけですぐに概要を把握できるよう、具体的な目次項目を設定しましょう。目次名から本文の内容を推測できない場合、マニュアルの検索機能が低下してしまいます。
| OK例 | 目次項目が具体的でひと目で概要を把握できる |
|---|---|
| NG例 | 目次項目から本文の内容を推測できない |
3-5.配色
マニュアルで使用する色は、まずテーマとなる1色を設定し、使用する色の数を絞り込むのがポイントです。その際は、面積の大きい順に「ベースカラー」「メインカラー」「アクセントカラー」の3色の比率が「70:25:5」になるように配色すると見やすくなります。また、読者の目が疲れにくい色使いを意識しましょう。
| OK例 | 3色程度の色使いでバランス良くまとめている |
|---|---|
| NG例 | 多数の色を使っている、目がチカチカする色使いをしている |
3-6.関連情報をまとめる
関連する情報をグルーピングして配置した構成にすると、読者が理解しやすくなります。その際は、余白や文字の装飾などを活用して、視覚的に関連情報であると示すことが大切です。反対に、関連情報が点在している構成ではページの行き来が多く発生し、読者のストレスになるため注意しましょう。
| OK例 | 関連するテキスト・画像・動画などが近くに配置されている |
|---|---|
| NG例 | 関連情報が全体へバラバラに配置されている |
3-7.図や表の活用
複雑な手順や文章だけでは理解が難しい内容は、積極的に図表を活用することで、読者の理解を助けられます。場合によっては写真・イラスト・図形のほか、動画を挿入しても良いでしょう。同じページ内に複数の図表を配置するなら、大きさを揃えて並べるなどレイアウトに工夫すると見やすいマニュアルになります。
| OK例 | 必要に応じて文章の内容を図表で補足しながら説明している |
|---|---|
| NG例 | 文章のみで説明している |
3-8.配置を揃える
文章の書き出しや図表の位置を決めるときは「Zの法則」を参考に配置を揃えると良いでしょう。Zの法則では、人間の視線の動きに合わせて「左上・右上・左下・右下」の順に情報を配置するのが基本的なルールです。文章や図表の端を揃えて整然と配置すると、きれいな印象の見やすいマニュアルになります。
| OK例 | 文章の書き出しや図表の位置が整っている |
|---|---|
| NG例 | 配置に凹凸やばらつきがある |
4.見やすいマニュアルのレイアウトを考えるときの注意点
見やすいマニュアルのレイアウトを考える際は、以下のポイントに注意しましょう。効率的なマニュアル化のヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
4-1.デザインにこだわり過ぎない
業務マニュアルは、現場のスタッフにとって見やすくて、内容がわかりやすいものが理想的です。そのため、必ずしも芸術的に美しいデザインにこだわる必要はありません。現場では、必要な情報が整理されたシンプルなデザインのマニュアルが求められています。シンプルなマニュアルは、利用者にとって読みやすいだけでなく、作成者がフォーマット化しやすいのがメリットです。
4-2.フォーマットを統一する
社内に優れたマニュアルテンプレートがすでに用意されている場合は、使い回してフォーマットを統一しましょう。新たにマニュアルを作成する場合は、フォーマット化してほかのマニュアルに転用できる状態にするのがおすすめです。このようにマニュアルテンプレートを用意しておくと、マニュアル作成の手間が減るだけでなく、品質が均一化されて作成者ごとのばらつきが少なくなります。また、利用者が読み慣れた形式に統一することで、マニュアルの内容を理解しやすくなるのもポイントです。
4-3.記載する情報の粒度を調整する
マニュアルでは情報を過不足なく伝えることが重要です。余計な文章はできるだけ削ぎ落とし、必要な情報が端的に伝わり、読むだけで誰もが再現できる状態を目指しましょう。文章量やページ数が過剰な場合は、利用者を離脱させるおそれがあります。ただし、文章を削ぎ落とし過ぎて抽象的な説明にならないよう、情報の粒度は適切に調整してください。
4-4.定期的に更新、修正を行う
一度作成した業務マニュアルは、定期的に更新を行い、適宜修正を加えましょう。長期間にわたりマニュアルの運用を続けると、記載されている内容が古くなり、マニュアルとして機能しなくなるおそれがあります。こうした理由から、マニュアルの作成後は定期的な整備が不可欠です。現場のフィードバックを受けながら改善を繰り返すことで、マニュアル導入の効果を高められます。
5.マニュアルを作成するときのコツ
マニュアル作成は時間と手間のかかる作業であるため、技術的・心理的に担当者の負担となるケースが少なくありません。社内でマニュアル作成を進める際は、以下のコツを押さえておきましょう。
5-1.完璧である必要はない
完璧なマニュアルを目指すのは悪いことではありませんが、担当者の負担が増えやすい点に注意しましょう。例えば、文章執筆や動画編集で細部までこだわると、その分だけ担当者の労力が増えることになります。結果としてマニュアルの作成や更新が遅れたり、プロジェクトが完全にストップしたりするおそれがあります。
最初から完璧なマニュアルを目指すよりも、更新を前提としたマニュアル作りを意識すると良いでしょう。まずは必要最低限の情報を記載し、その後に適宜情報をアップデートするのも一つの方法です。一旦、現状で必要な情報のみ記載する方針にすれば、担当者の負担が過剰になるリスクを避けやすくなります。
5-2.心理的障壁を無くすように作る
せっかく作成したマニュアルを現場のスタッフになかなか読んでもらえないケースもあるでしょう。その際は、読者の心理的障壁を無くすために、さまざまなテクニックを取り入れるのがおすすめです。
例えば、特に注目してほしい情報に目立ちやすいアイコンをつける方法が挙げられます。また、読み手の立場に立った短いメッセージを入れることで、心理的な負担が軽くなることもあります。新人教育などのプレッシャーを感じやすい場面では、読者の理解度に配慮しながら、安心して業務を遂行できるよう寄り添ってあげましょう。
こうしたテクニックで心理的障壁が無くなると、社内でマニュアルの活用が促進され、業務効率化や属人化解消の効果が向上すると期待できます。また、マニュアル作成の担当者が自分なりに創意工夫することで、やりがいを感じやすくなるというメリットもあります。
5-3.作成手順や準備について
マニュアル作成のプロジェクトでは、人材や作業時間などのリソースを確保する必要があります。完成までにどの程度の期間がかかり、どの程度の労力を割くことになるのか、スケジュール管理が不可欠です。締め切りまでにマニュアルを完成させるためにも、進捗管理を徹底しましょう。
マニュアルを効率的に作成して、できるだけ社内の負担を軽減するためにも、担当者がマニュアル作成の手順を把握しておくことが大切です。以下の関連記事では、マニュアル作成の流れについて詳しく解説しているため、ぜひ本記事と併せて確認してみてください。
【関連記事】わかりやすい業務マニュアルの作り方とは?作成手順とポイント
6.見やすいマニュアルの作り方ではレイアウトが重要!
ここまで、見やすい業務マニュアルの作り方について解説しました。見やすいマニュアルを作成するには、マニュアル内のレイアウトに配慮することが大切です。また、必要に応じて図表を使用したり、情報を適切に階層化したりするテクニックによって、大事なポイントをより効率的に伝えられます。
これらの要点を押さえて、読み手のスムーズな理解を助けるマニュアルを作るなら、専用の作成ツールを導入してはいかがでしょうか。そこでおすすめなのが、現場での使いやすさとわかりやすさにこだわったマニュアル作成ツール「Dojoウェブマニュアルフリー」です。
「Dojoウェブマニュアルフリー」は、スマホを使って誰でも簡単にマニュアルの作成・共有ができます。無料で導入可能で、有料版と同等の充実した機能を使えるのが魅力です。作成したマニュアルはWeb上で確認できるため、紙のマニュアルを持ち歩く必要がなく、紛失したり破損したりする心配がありません。
また、画像や動画を活用して簡単に解説できるため、文章だけでは説明が難しい内容をよりわかりやすく伝えることができます。時短とフォーマットの統一を同時に叶えられるので、初めてのマニュアル作成でも安心です。
「Dojoウェブマニュアルフリー」は無料のため、ぜひお気軽に導入をご検討ください。無料版は以下のページからお申し込みいただけます。マニュアル作成の負担を軽減しながらクオリティを高めるなら、「Dojoウェブマニュアルフリー」にお任せください。
無料で簡単マニュアル作成『Dojoウェブマニュアルフリー』を詳しく見る
【業務改善ならDojoシリーズ。マニュアル作成の悩みをカンタン解決!資料ダウンロード】 はこちら。